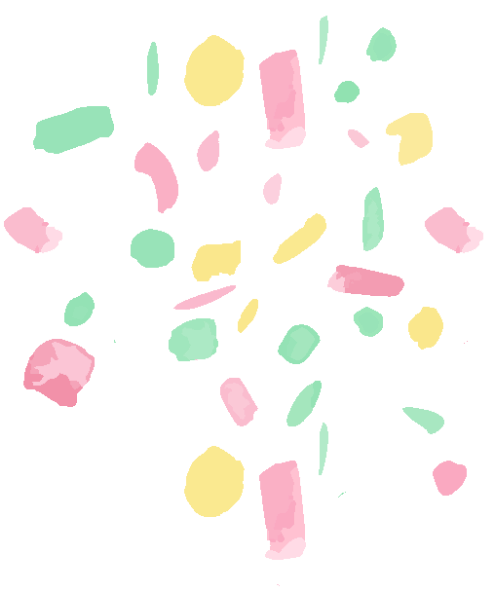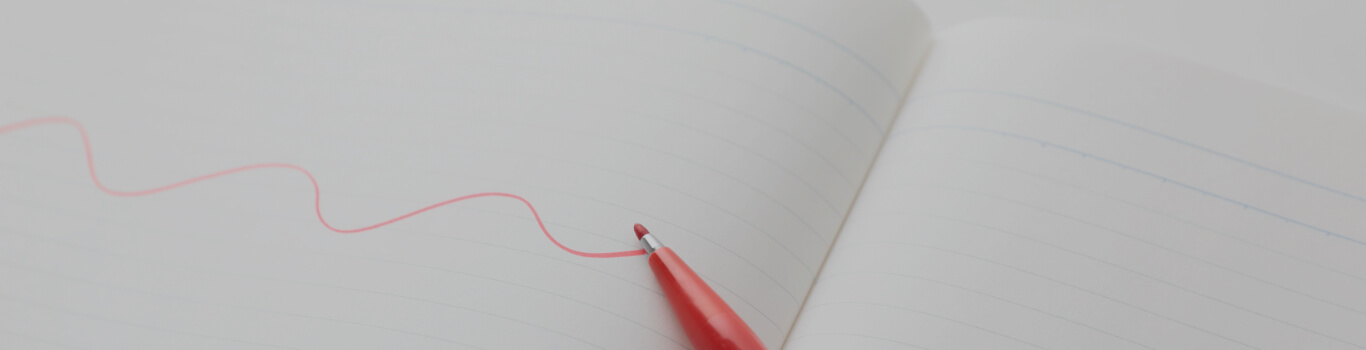ぺんてるのインターンシップ


ぺんてるを、ユーザー目線ではなく、
社員目線で捉える。
ぺんてるの製品は皆さんにとって身近なものだと思います。新たな表現を形にするために、ぺんてるは日々アイデアと想いを表現具をつくるという手法で世の中に対して、「表現」しています。
そんなぺんてるをユーザーとしてではなく、社員目線で深く知ることのできるコンテンツをご用意。
事業や仕事だけでなく、社員のリアルな姿や雰囲気を感じてもらえる機会でもありますので、ぜひご参加ください。

文具業界とぺんてるを体感する
2つのコンテンツ
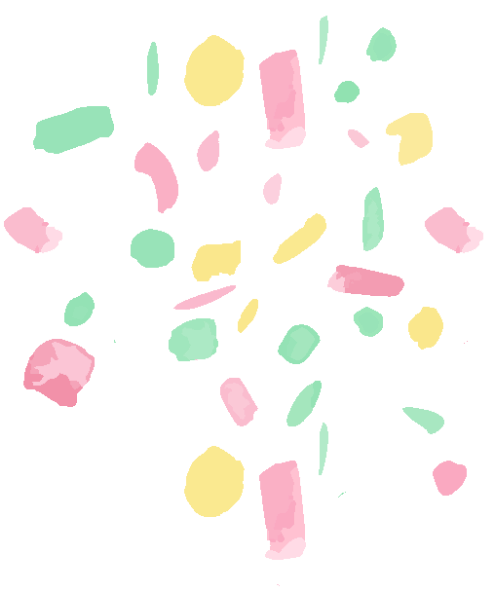

Contents A
ぺんてるの1DAY仕事体験
文系・理系の各職種に焦点を当て、文具業界のこと、当社の強み・こだわり、実際の仕事内容・やりがいについて、先輩社員と一緒に、ワークを通して学んでいただきます。
当日のプログラム
- 1.業界企業研究
-
文具業界の現状・今後の展望などお伝え致します。
「消費者」として皆さんにとって身近な存在でもある文房具ですが、それを生み出す業界・企業がどのような価値を社会に与えているのか、実際に「働く」という視点で考えてみてください。
- 2.社員による仕事紹介
-
文具業界での仕事についてどのようなイメージを抱いていますか?
より具体的に仕事をイメージしていただけるよう、実際に現場で働く社員の声をお届けします。
- 3.仕事体感ワーク
-
理系向け
研究・開発現場の先輩社員からアドバイスを受けながら、「ぺんてる×わたし」をテーマにアイデアを出し合い提案をしていただきます。文系向け
製品知識を学び、お客様に売り場の企画提案をしていただく、商談のロールプレイングを行います。
- 4.先輩社員との懇談会
- 皆さんからのご質問、相談に先輩社員がお答え致します。
今後の活動の参考にしていただけますと幸いです。
参加先輩社員の例
理系向け

S社員

T社員

M社員
文系向け

K社員

Y社員

N社員
こんな人におすすめ
- 文具や筆記具が好き
- 生活の身近なところで活躍するものづくりに携わってみたい
- 具体的な仕事内容について話を聞いてみたい

Contents B
ぺんてる体感セミナー
パネルディスカッション・座談会を中心とするセミナーです。
当社への疑問・質問を解決し、ぺんてるの社風を感じ取っていただける内容となっています。
当日のプログラム
- 1. パネルディスカッション
- ぺんてるについて、そして文具業界についての疑問・質問を取り上げて先輩社員とのパネルディスカッションを展開いたします。
※当日は冒頭に、皆様にぺんてるへの「質問カード」をご記入いただきます。皆様にご記入いただいた内容を元にお話を進めさせていただく予定です。
- 2. 座談会
- 皆さんからのご質問、相談に先輩社員がお答え致します。
今後の活動にお役立ていただけますと幸いです。
- 3. 今後のスケジュール
-
最後に、今後のスケジュールにつきまして皆様にご連絡をさせていただく予定です。
就職活動に向けて、先輩社員からのアドバイスもありますのでぜひ参考にしてみてください。
参加先輩社員の例
理系向け

H社員

K社員

D社員
文系向け

K社員

I社員

Y社員
こんな人におすすめ
- ぺんてるで働きたい
- 多くの先輩社員に話を聞いてみたい
- 直接聞いてみたいことがある
実施スケジュール
| 日程 | ぺんてるの 1DAY仕事体験 |
ぺんてる 体感セミナー |
||
|---|---|---|---|---|
| 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | |
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||

※スケジュール・内容は変更する可能性もございます。
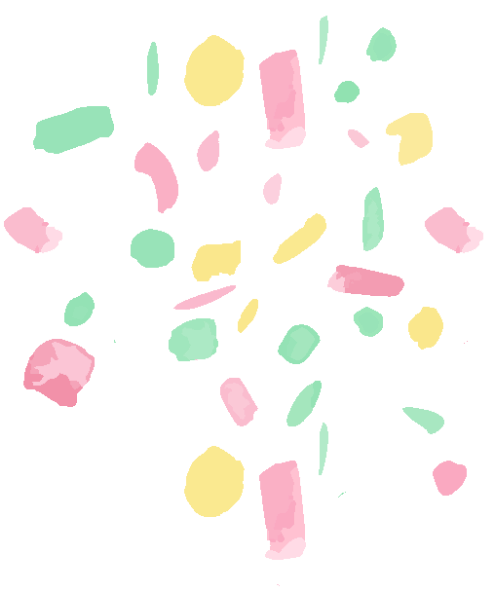
参加者の声
理系
大学時代の研究内容がどのように仕事に活かせるか考えられる良い機会になったと思います。それにより面接時に自分のやりたいことを明確に示せました。
「何事にも好奇心を持って取り組む」「他者の意見を尊重しより良くしたい」という、ぺんてる社員の人柄の良さに触れることができたインターンシップでした。
現場で働く社員の方々から直接具体的な仕事内容について聞けるので、”自分のこれまでの学びを活かせるフィールド”が明確となり、実際に働く姿をイメージ出来るようになりました。
文系
文具業界の現状や企業の特長・強みについて学ぶことができ、また営業の商品紹介のロールプレイングを通じて、営業活動の雰囲気を体感することができました。
ワークショップを通じて、営業として働く際の具体的なイメージをすることができました。営業社員は限られた時間でいかに要点を伝えられるか、その一方でお客様との会話も大切だと知りました。
文具業界についてやぺんてる商品のカテゴリーの幅広さを学ぶことができました。文具メーカー営業がどのようなことをするのかもとてもわかりやすかったです。

最後に