表現フィールドリサーチ
世界中の子どもたちが“描く”でつながる! 「世界一大きな絵」プロジェクト

みなさんは「世界一大きな絵」というプロジェクトをご存じでしょうか?描いているのは著名な画家やデザイナーではなく、世界中の子どもたち。彼らが自由にのびのびと描いた絵をつなぎ合わせることで、国・宗教・人種を越えた壮大な一枚が完成するという、世界を股に掛けたプロジェクトです。今回は、そんなスケールの大きなプロジェクトをスタートさせ、今日まで成長させてきたNPO法人「アース・アイデンティティー・プロジェクツ」の取り組みについて探ってみました。
01プロジェクトの主役は、世界中の子どもたち。
クレヨン、色鉛筆、絵の具––––。
私たちは小さな頃からさまざまな画材に触れていますが、それは学校などで“描く”ことを教わっているからこそ。画材があれば描けるものではなく、教育環境が整っていない国では、画材の使い方はもちろん、“描く”ということさえ身近ではない子どもたちがいるのです。
そんな当たり前のことに気付かされるプロジェクトこそ、NPO法人「アース・アイデンティティー・プロジェクツ」が主催する「世界一大きな絵」。日本人が中心となり1996年よりスタートしたこのプロジェクトは、世界各国の子どもたちが描いた布のキャンバスをつなぎ合わせ、一枚の巨大な絵に仕立て上げるというもの。一見するとシンプルな活動内容ですが、国や地域が変われば描く環境は千差万別。例えば、サウジアラビアでは気温50度にもなるカンカン照りの砂漠の真ん中に絨毯を敷き詰めて描く、なんていうことも。描かれた場所の土地柄や歴史的背景を知ると、描かれた絵の見方も変わってくるのではないでしょうか。

1996年12月バングラデシュ/クリグラム
このプロジェクトが広く世界に知られたのは、1996年のこと。バングラデシュで試験的に開催した初めての取り組みがきっかけでした。この様子が世界中で報道され、同国ではチャリティーコンサートを行なったビートルズに次いで賞賛されるほどの偉業となったのです。
それ以来、世界各地で子どもたちの描いた絵をつなぎ続けてきた「世界一大きな絵」プロジェクト。現在は、2024年夏のフランス開催に向けて着々と準備が進められています。
02「子どもたちに絵を描かせたい」。すべてはシンプルな想いからはじまった。
2022年10月には、2年後のフランス開催に向けたキックオフイベントが大田区総合体育館で実施されました。元々は2020年3月に予定していたものの、コロナ禍で延期に次ぐ延期に…。開催2ヶ月前までさまざまなプログラムを用意して、たくさんの子どもたちを迎え入れて大々的なイベントにする予定でしたが、新型コロナ感染拡大のニュースを受けてやむなく規模縮小での開催を決断。無観客の中、広い体育館に運営側で絵を並べ、ピアニストによる演奏や歌手による独唱とともに写真、動画、ドローン等を駆使して映像を作成する方向になりました。
今回私たちはそのキックオフイベントにお邪魔させていただくことに。会場である体育館に足を踏み入れると、これまで描かれたうちの“ほんの一部”という絵が1,824平米の巨大なアリーナいっぱいに敷き詰められていました。

その中央で、絵の組み合わせやバランスを指示している女性の姿が。この方こそが、本プロジェクトの発起人であるNPO法人「アース・アイデンティティー・プロジェクツ」会長の河原裕子さんです。

NPO法人「アース・アイデンティティー・プロジェクツ」会長の河原裕子さん
そもそも、なぜこの壮大なプロジェクトをスタートさせたのか、河原さんに伺ってみると。
「バングラデシュの最貧地区で、約10,000人の女性の自立支援を行っていたことが、そもそものきっかけ。プロジェクト開始当初のバングラデシュは学校もなく、石板などの勉強道具もないから、土の上に文字を書いて勉強していたの」
絵や文字を書く文具さえ買えない国がある中、1990年代に“アジアの最貧国”と呼ばれていたバングラデシュは、その最たるもの。1986年より縁あってバングラデシュに滞在していたという河原さんは、ある日、現地で活動を共にするグラフィックデザイナーの稲吉紘実さんから「子どもたちに絵を描かせたい」との想いを伝えられたそう。

1996年12月バングラデシュ。1000人のお母さんの手によって一枚一枚絵が縫い合わせられていく様子。
当時、稲吉さんから何人の子どもを集められるかと聞かれた河原さんは、総勢13,200人の子どもたちを集めました。
「私が自立支援を行なっていた10,000人のお母さん1人に対して、5人も10人も子どもがいたんですよ。だから、その中からお子さん1人ずつに参加してもらい、絵を描いてもらったんです」
10kmもの布を裁断し、1m✕10mの布1,000枚に子どもたちに絵を描いてもらい、1,000人のお母さんが縫い合わせた100m四方の「世界一大きな絵」。その巨大な一枚は、バングラデシュの未来を象徴するシンボルとして大きな話題を呼んだのです。
03描くこと。それは、子どもたちにとって一生に一度の経験だった。
“世界一大きな絵”というプロジェクトが何なのかもわからずに、夢中になって絵を描いていたという現地の子どもたち。その姿を思い浮かべながら河原さんは言葉を続けます。
「子どもたちはこのプロジェクトのことがわからないだけではなく、絵の描き方もわからないんです。いつも裸で過ごしている彼らが服を着て、コインの裏に描かれている魚を真似て描いたり、国旗を描いたり––––。使ったことのない画材を手に、布のキャンバスと一対一で向き合うその熱量は本当に凄かったんですよね」
子どもたちがそこまで真剣に絵と向き合っていたのは一体なぜなのでしょうか?その理由を尋ねてみると。
「彼らにとっては、もう一生絵を描くことはないかもしれないから……」
当時のバングラデシュのような発展途上国では、子どもが絵の描き方を教わる機会は極めて少なく、絵を描かずに一生を終えるということも。表現するよろこびを知らなかった子どもたちが、まるで水を得た魚のように無我夢中でキャンバスと向き合い自由に描いていく様子。そんな子どもたち一人ひとりの姿が「世界一大きな絵」プロジェクトの原点として、河原さんの目に焼き付いているようです。
その後も、プロジェクトの輪は広がり続け、“描く”を介してさまざまな国との交流も増えていったのだそう。
「ある国で開催したときには、国際交流プロジェクトの一環で、日本の子どもたちも一緒に参加できたんです。そこで色々な国の子どもたちが集まって一緒に絵を描いていったんですが、キャンバスに描くだけではなく、自分やお友だちの身体に絵を描いてみたりと自由に楽しんでいて。子どもたちの奔放な発想力と筆遣いに驚き、楽しませてもらいました」

自由な筆遣いから、描くよろこびが伝わってくる。

これまで布に描く画材はぺんてるの絵の具を愛用してくれていたというのも嬉しい。
作品に描かれるモチーフも色使いも、本当にさまざま。なぜここまで作風に違いが出るのか疑問に思っていると。
「私自身が子どもの頃に、絵が下手とか言われたんですよ。そう言われてしまうと、いじけるじゃないですか。だからプロジェクトで子どもたちに絵を描いてもらうときは、“あれはダメこれもダメ”なんてことは絶対に言わないようにしているんです」
河原さんの原体験もあってか、本プロジェクトにテーマは一切なし。作品を見渡してみると、特産物に似顔絵に手形に国旗と、思いのままに子どもたちが描いているところは、初回のバングラデシュでのプロジェクトと何ら変わらないのかもしれません。
04巨大なキャンバスが世界をつなぎ、未来へとつながっていく。
「絵からエネルギーをもらえるのよね」
そう河原さんが笑顔で語るように、子どもたちのピュアなエネルギーが込められた絵は、著名な芸術家の一枚にも匹敵する力を感じます。また面白いことに、絵の具やクレヨンといった同じ画材を使用していたとしても、色使いや筆遣いひとつで「日本の作品ではないな……!」と、お国柄が見て取れるところも世界一大きな絵の楽しみ方かもしれません。

色使いや描かれるモチーフにもその国の文化が表れている。


この日取材に訪れた私たちのために自らの言葉で作品の説明をしてくれる河原さん。その精力的な姿にこの活動にかける情熱を感じます。
2023年以降もフランス開催に向けたイベントは国内外で予定されており、現在も着々と準備が進められている模様ですが、そもそもこのプロジェクトを続けることの意味とは––––。
「子どもたちが自由に表現して描く。そんな時間そのものが尊く、それこそが平和なんだと思っていて」
絵を描くことが当たり前ではない国の子どもたちには、厳しい環境が日々待ち続けています。けれども、夢中になって筆を動かしている時間は、辛いことも忘れられる心踊るような楽しいひとときなのかもしれません。プロジェクトを通して何か大きなことを成し遂げるのではなく、自由に表現できる平和な時間を生み出す。活動そのものに大きな意義を感じました。

「何でも自由に描いていいからねって言うと、みんなびっくりするんですよね。学校だと『これを描きましょう』とテーマが与えられますが、何を描いてもいいと言うと一回怯むんですよ。けれども子どもたちは、ひと呼吸置いてからワーッて描き出すんです。それでいいんですよ」
以前からぺんてるの絵の具をプロジェクトの中で使ってくれていたという河原さん。2022年からはぺんてるも本プロジェクトを正式にサポートしています。
1996年から2024年に向けて。そして、その後もきっと増え続けていくであろう絵は、子どもたちの大切な思い出として残りながら、世界をつなぎ、未来へとつながっていくシンボルとなっていくはずです。




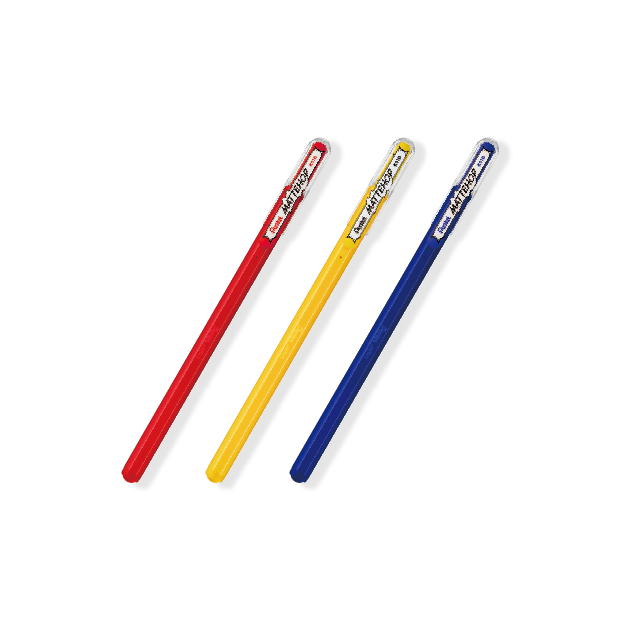
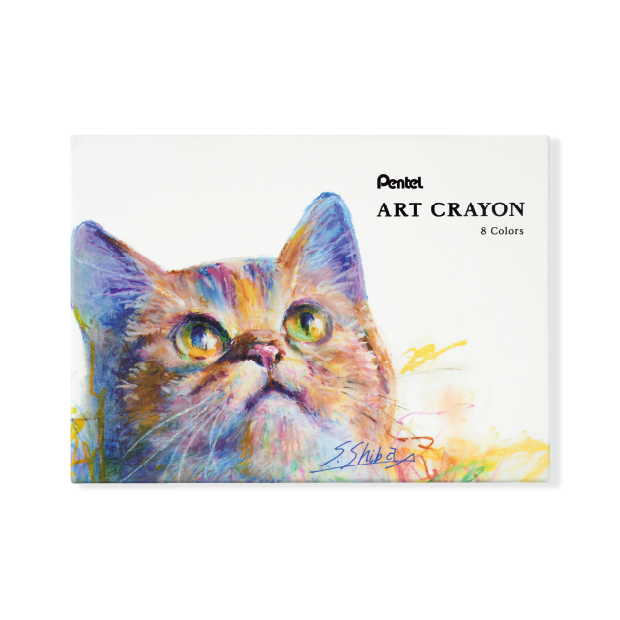
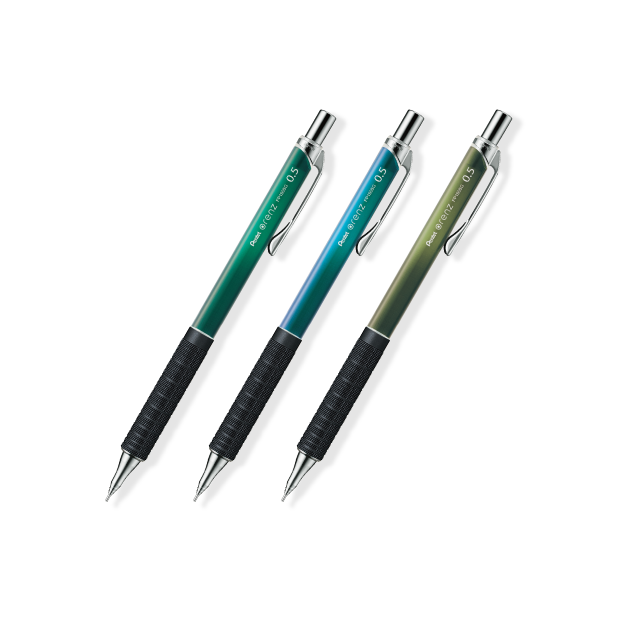
 Xでシェアする
Xでシェアする Facebookでシェアする
Facebookでシェアする LINEでシェアする
LINEでシェアする
